- HOME >
- 令和元年度(第22回)ケアマネージャー試験問題(3月実施分) >
- 【分野別一問一答】保健医療福祉サービス分野(基礎)
第22回 介護支援専門員 実務研修受講試験問題(3月実施分)【解答・解説】学校法人 藤仁館学園
保健医療福祉サービス分野(基礎) 一問一答
問26
高齢者に多い症状・疾患について正しいものはどれか。3つ選べ。
1加齢黄斑変性では、進行すると視力が失われる恐れがある。
2高齢者のめまいは、内耳の障害のほか、血圧のコントロール不良、脳腫瘍などが原因となることがある。
3高齢者の難聴では、感音性難聴が多い。
4心房細動では、心内で形成された血栓による脳梗塞は発症しない。
5服用する薬剤数が多くても、副作用のリスクは増大しない。
問27
高齢者のてんかんについて、より適切なものはどれか。2つ選べ。
1初回発作後の再発率は、低い。
2発作の間は、誤嚥を予防するための対応をする。
3意識障害、しびれ、発汗、けいれんなど多様な症状を呈する。
4最も多い原因は、脳腫瘍である。
5治療は、放射線療法により行う。
問28
認知症について適切なものはどれか。2つ選べ。
1中核症状には、記憶障害、見当識障害などがある。
2BPSD(認知症の行動・心理症状)の悪化要因として最も多いのは、家族の不適切な対応である。
3認知症患者の精神科病院への措置入院は、精神保健指定医ではない主事の医師による診断のみでも、緊急時においては可能である。
4若年性認知症患者が入院に依る精神医療を必要とする場合には、自立支援医療の対象となる。
5認知症初期集中支援チームは、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を複数の専門職が訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行う。
問29
皮膚疾患について、より適切なものはどれか。2つ選べ。
1薬疹は、長期間服用している薬剤により生じることはない。
2寝たきりで関節拘縮のある場合には、特定の部位に圧力が集中して褥瘡が生じやすいので、耐圧分散寝具を使用するのがよい。
3皮脂欠乏症では、患部を清潔に保つことが悪化予防になることから、ナイロンタオルを使ってよく洗う。
4白癬は家族内で感染することはまれであるため、爪切りやスリッパなどは共用しても差し支えない。
5脂漏性湿疹では、患部を清潔に保つほか、抗真菌薬などを使用する。
問30
次の記述について適切なものはどれか。3つ選べ。
1喫煙は、皮脂異常症、高血圧症とともに虚血性心疾患のリスクファクターである。
2健康日本21(第二次)では、健康寿命の延伸だけでなく、健康格差の縮小も目標に掲げている。
3老年期うつ病では、対人関係で攻撃性が増すため、自死を図ることは稀である。
4老年発症型のアルコール依存症では、家族歴や遺伝的要因を有することが多い。
5老年期のアルコール依存症では、離脱症状が遷延しやすい。
問31
検査について、より適切なものはどれか。3つ選べ。
1ヘモグロビンA1cの値は、過去1~2か月の血糖レベルを反映している。
2大動脈疾患や進行した動脈硬化の場合は、左右の上肢で血圧に差がみられることがある。
3ノロウイルス感染症では、下痢などの症状がなくなれば、感染力もなくなる。
4CRP(C反応性たんぱく質)は、感染症以外に、悪性腫瘍や膠原病でも高値になる。
524時間心電図(ホルター心電図)検査は、医療者による継続的な観察が必要な、入院して実施しなければならない。
問32
薬剤に関する次の記述について適切なものはどれか。3つ選べ。
1パーキンソン病の治療薬であるドーパミン製剤は、服用を突然中止すると、高熱、意識障害、著しい筋固縮などを呈する悪性症候群を生じる恐れがある。
2高齢者は腎機能が低下しているため、薬の副作用が減弱することが多い。
3胃ろうから薬剤を注入する際には、それぞれの薬剤について、錠剤を粉砕したり、微温湯で溶解させたりしてよいか、確認する必要がある。
4口腔内で溶けるOD(Oral Disintegrant)錠は、口腔粘膜からそのまま吸収される薬剤である。
5症状が消失すると内服を自己判断でやめてしまう場合があるため、内服状況を確認する必要がある。
問33
次の記述について正しいものはどれか。2つ選べ。
1胃ろうがある場合には、原則として、入浴は禁止されている。
2終末期においては、嚥下機能が低下して肺炎を起こしやすいので、口腔ケアは行わない。
3膀胱留置カテーテル使用中は、尿路感染を予防するため、毎日膀胱洗浄を行う。
4糖尿病の内服治療をしている者では、インスリン注射をしていなくても、低血糖の症状に留意する必要がある。
5認知症治療薬には、錠剤以外にも経皮吸収型などがあり、経口内服が困難な高齢者でも使用が可能である。
問34
在宅医療について正しいものはどれか。2つ選べ。
1インスリンの自己注射の効果は、体調不良時(シックデイ)には強く出ることもある。
2悪性腫瘍の疼痛管理のための麻薬の投与経路には、経口、経皮、経腸、注射がある。
3人工透析を行っている場合には、シャント側で血圧測定を行う。
4侵襲的陽圧換気法(IPPV)による人工呼吸は、マスクを装着して行われる。
5酸素マスクによる在宅酸素療法は、鼻カニューレによるものに比べて、食事や会話がしやすいのが特微である。
問35
次の記述について適切なものはどれか。3つ選べ。
1自己腹膜灌流法(CAPD)による人工透析は、血液透析に比べて、通院回数が少なくて済む。
2終末期にある者には、効果が期待できないため、リハビリテーションは実施されない。
3気管切開をしている場合でも、スピーチカニューレの使用により発生は可能である。
4慢性閉塞性肺疾患(COPD)により呼吸機能が低下している場合でも、インフルエンザワクチンの接種は推奨される。
5在宅酸素療法は、入院しなければ導入できない。
問36
高齢者の転倒について適切なものはどれか。3つ選べ。
1要介護高齢者が短期間に複数回転倒した場合には、再度転倒する可能性が高いため、総合的にアセスメントを行い、対策を検討する必要がある。
2転倒を繰り返す介護施設入所者については、向精神薬などの薬物を用いて動けないように行動を制限する。
3転倒により頭部を強く打った場合には、数時間様子をみて、意識障害などがなければ、それ以上の経過観察は要らない。
4高齢の女性は、骨粗鬆症が多いので、転倒により骨折を起こしやすい。
5夜間の排尿行動や不穏状態で転倒することが多い。
問37
リハビリテーションについて適切なものはどれか。3つ選べ。
1通所リハビリテーション計画は、主治の医師が作成しなければならない。
2回復期リハビリテーションでは、機能回復、ADLの向上及び早期の社会復帰を目指す。
3指定訪問リハビリテーションとは、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が居宅を訪問して行うリハビリテーションをいう。
4変形性膝関節症の発症リスクは、減量をしたり、大腿四頭筋等の筋力を鍛えたりしても、低下しない。
5左片麻痺でみられる半側空間失認に対しては、失認空間に注意を向けるリハビリテーションを行う。
問38
排泄について、より適切なものはどれか。3つ選べ。
1腹圧性尿失禁には、骨盤底筋訓練よりも膀胱訓練が有効である。
2便失禁は、全て医学的治療を要する。
3ポータブルトイレについては、理学療法士等の多職種と連携し、日常生活動作に適合したものを選択する。
4日常生活動作の低下による機能性失禁では、排泄に関する一連の日常生活動作の問題点を見極めることが重要である。
5排便コントロールには、排便間隔を把握し、食生活や身体活動等を含めた生活リズムを整えることが大切である。
問39
災害対応について適切なものはどれか。2つ選べ。
1福祉避難所の対象は、高齢者や障害者など避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者であり、その家族は含まない。
2災害時においても、個人情報保護の観点から、要援護者の個人情報の提供及び共有は、行うことができない。
3災害時の課題である生活不活発病は、活動低下により身体機能が低下した状態をいい、要介護者のみに生じる。
4深部静脈血栓症/肺塞栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)を予防するためには、定期的に体を動かし、十分に水分を摂るようにする。
5人工呼吸器等電源を必要とする医療機器使用者の停電時の対応については、平時より、主治の医師等と話し合い、対応を決めておく。
正解は…4・5
- 福祉避難所の対象者は、高齢者や障害者など、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者だけでなく、その家族も含まれる。
- 「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取扱方針(内閣府:2013年8月)」で、避難行動支援者名簿登録を推奨し、専門職のみならず、地域住民とも個人情報を共有することとしている。また、平常時から名簿情報を広く支援関係者に提供することを説明し、意思確認を行うことも必要である。
- 災害時の新たな課題である生活不活発病は、動かない(生活が不活発な)状態が続くことにより、心身の機能が低下して動けなくなることをいう。要介護者に限らず高齢者は、環境の変化により動きにくくなり、動かないことでますます生活不活発病を進行させてしまうため、早期に対応することが大切である。
- ○
- ○
問40
次の記述について、より適切なものはどれか。3つ選べ。
1がんの発症頻度は、年齢とともに高くなる傾向になる。
2臨死期には、死前喘鳴がみられることがあるが、首を横に向ける姿勢の工夫で軽減することもある。
3臨死期には、顎だけで呼吸する下顎呼吸状態となる場合があるが、しばらくすると正常な呼吸に戻る。
4呼吸困難や疼痛に対しては、到着のほか、安楽な体位やマッサージなどで苦痛の緩和を図る。
5高齢者のがんに対しては、侵襲性の高い手術療法は行うべきではない。
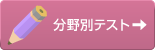
正解は…1・2・3