- HOME >
- 令和5年度(第26回)ケアマネージャー試験問題 >
- 【分野別一問一答】介護支援分野
第26回 介護支援専門員 実務研修受講試験問題【解答・解説】学校法人 藤仁館学園
介護支援分野 一問一答
問1
高齢化について正しいものはどれか。2つ選べ。
12025(令和7)年には、いわゆる団塊の世代が85歳に到達する。
22021(令和3)年国民生活基礎調査によると、65歳以上の者のいる世帯では「三世代世帯」の割合が一番多い。
3国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(平成30年推計)によると、世帯主が65歳以上の世帯数は2040(令和22)年まで増加し続ける。
4国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」(平成29年推計)によると、前期高齢者の人口は、2015(平成27)年と比べて2045(令和27)年では倍増する。
52019(令和元)年度末における85歳以上の介護保険の被保険者に占める要介護又は要支援と認定された者の割合は、50%を超えている。
問2
地域福祉や地域共生社会について正しいものはどれか。3つ選べ。
1市町村は、包括的な支援体制を整備するため重層的支援体制整備事業を実施しなければならない。
2市町村は、市町村地域福祉計画を策定するよう努めるものとする。
3地域共生社会とは、子供・高齢者・障害者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる社会のことである。
4介護保険法に基づく地域支援事業等を提供する事業者が解決が困難な地域生活課題を把握したときは、その事業者が自ら課題を解決しなければならない。
5高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスは、介護保険制度と障害福祉制度の両方に位置付けられている。
正解は…2・3・5
- 市町村は、本事業を適切かつ効果的に実施するため、「重層的支援体制整備事業実施計画」を策定するよう努めることとしている(社会福祉法第106条の5)
- 記述の通り。市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画を策定するよう努めるものとする(社会福祉法第107条)
- 記述の通り。地域共生社会とは、8050(9060)問題や育児と介護のダブルケア、社会的孤立など、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会をいう。
- 介護保険法に基づく地域支援事業等を提供する事業者が、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない(社会福祉法第106条の2)
- 記述の通り。共生型サービスは2018年に創設され、対象となるサービスは、高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用される介護保険と障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス、現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービスとしており、具体的には、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイがある。
問3
社会保険について正しいものはどれか。2つ選べ。
1雇用保険は、含まれない。
2自営業者は、介護保険の被保険者にならない。
3医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とする。
4年金保険は、基本的に任意加入である。
5財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心であるが、国・地方公共団体や利用者も負担している。
問4
介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。3つ選べ。
1要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われなければならない。
2被保険者の置かれている環境に配慮せず提供されなければならない。
3可能な限り、被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
4医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
5介護支援専門員の選択に基づき、サービス提供が行われなければならない。
正解は…1・3・4
- 記述の通り。保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない(介護保険法第2条2)
- 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条3)
- 記述の通り。保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない(介護保険法第2条4)
- 記述の通り。保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない(介護保険法第2条2)
- 介護支援専門員の選択ではなく、利用者本人の選択に基づき、サービス提供が行われなければならない(介護保険法第2条3)
問5
介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれか。3つ選べ。
1介護老人福祉施設
2地域密着型介護老人福祉施設
3有料老人ホーム
4介護老人保健施設
5認知症対応型共同生活介護
問6
65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならないものはどれか。2つ選べ。
1老人福祉法に規定する養護老人ホームの入所者
2児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者
3生活保護法に規定する更生施設の入所者
4生活保護法に規定する救護施設の入所者
5児童福祉法に規定する母子生活支援施設の入所者
問7
介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。
1労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。
2労働者災害補償保険法の介護保障給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。
3介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。
4生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。
5障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。
問8
介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。2つ選べ。
1居宅介護サービス計画費の支給
2特定入所者介護サービス費の支給
3居宅介護福祉用具購入費の支給
4高額介護サービス費の支給
5高額医療合算介護サービス費の支給
問9
介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1医師の診断書に基づき居宅サービス計画を作成しなければならない。
2要介護者のため忠実に職務を遂行しなければならない。
3自らサービスの質の評価を行うこと等により常に利用者の立場に立ってサービスを提供するように努めなければならない。
4利用者が居宅において心身ともに健やかに養護されるよう、利用者の保護者を支援しなければならない。
5法令遵守に係る義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備しなければならない。
正解は…2・3・5
- 居宅サービス計画を作成するのは居宅介護支援事業者であり、指定居宅サービス事業者が作成するものではない。居宅サービス事業者は居宅サービス計画に基づき、個別介護計画を作成する。また、居宅介護支援事業者が、居宅サービス計画を作成する際に、医師の診断書に基づいて作成するという規定はない。
- 記述の通り(介護保険法第74条第6項)
- 記述の通り(介護保険法第73条第1項)
- 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。支援対象として、利用者の保護者に関する規定はない。
- 記述の通り(介護保険法第115条の32第1項)
問10
介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析について正しいものはどれか。3つ選べ。
1市町村は、介護保険等関連情報を分析した上で、その分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
2都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要はない。
3都道府県は、介護サービス事業者に対し、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報を提供しなければならない。
4厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
5厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができる。
問11
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する基金(地域医療介護総合確保基金)について正しいものはどれか。3つ選べ。
1医療及び介護の総合的な確保に関する目標を達成するために必要な事業に要する費用を支弁するため、都道府県が設ける。
2公的介護施設等の整備に関する事業は、支弁の対象とならない。
3医療従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。
4介護従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。
5国が負担する費用の財源は、所得税及び法人税である。
正解は…1・3・4
- 記述の通り。団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務となり、これらの取組みを推進するため、2014年度から消費税増収分を活用した「地域医療介護総合確保基金」を各都道府県に創設し、財政支援を行っている。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づいて事業を実施している。
- 介護施設等の整備に関する事業は対象となっている(都道府県計画に基づき実施される「地域密着型サービス施設等の整備」「介護施設の開設準備経費等」「特養多床室のプライバシー保護のための改修等」等)
- 記述の通り。医療従事者の確保に関する事業(都道府県計画に基づき実施される「医師確保対策」「看護職員等確保対策」「医療従事者の勤務環境改善対策」に資する事業)は対象となっている。
- 記述の通り。介護従事者の確保に関する事業(都道府県計画に基づき実施される「参入促進」「資質向上」「労働環境・処遇の改善」に資する事業等)は対象となっている。
- 国が負担する費用の財源には、消費税財源を活用する。
問12
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として正しいものはどれか。2つ選べ。
1医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。
2第1号被保険者の保険料に係る特別徴収を行う。
3都道府県に対し介護給付費交付金を交付する。
4市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。
5介護保険サービスに関する苦情への対応を行う。
問13
地域支援事業の包括的支援事業として正しいものはどれか。2つ選べ。
1家族介護支援事業
2一般介護予防事業
3在宅医療・介護連携推進事業
4保健福祉事業
5生活支援体制整備事業
問14
地域ケア会識の機能として正しいものはどれか。3つ選べ。
1個別課題の解決
2地域づくり・資源開発
3政策の形成
4地域包括支援センターから提出された事業計画書の評価
5日常生活自立支援事業の生活支援員の指名
問15
介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
1従業者の個人情報保護等のために講じる措置
2従業者の教育訓練の実施状況
3年代別の従業者の数
4従業者の労働時間
5従業者の健康診断の実施状況
問16
介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1介護支援専門員の資格に関する処分
2指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分
3財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分
4要介護認定に関する処分
5被保険者証の交付の請求に関する処分
問17
介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。
1償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。
2法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。
3滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。
4介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
5介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
問18
要介護認定の申請について正しいものはどれか。2つ選べ。
1被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない。
2地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができる。
3介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。
4要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない。
5更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる。
問19
要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。
2申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。
3新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。
4一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。
5審査及び判定の基準は、市町村が定める。
問20
定居宅介護支援について正しいものはどれか。3つ選べ。
1介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成に当たっては、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
2事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行わなければならない。
3指定居宅介護支援の提供に当たっては、公正中立に行われなければならない。
4介護支援専門員の連絡調整の対象は、指定居宅サービス事業者に限定される。
5事業者の連携の対象には、障害者総合支援法の指定特定相談支援事業者は含まれない。
正解は…1・2・3
- 記述の通り。介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成に当たっては、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるように努めなければならない。
- 記述の通り。指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行わなければならない。
- 記述の通り。指定居宅介護支援の提供に当たっては、公正中立に行われなければならない。
- 介護支援専門員の連絡調整の対象は、指定居宅サービス事業者に限定されず、市町村、医療機関など広範にわたる。
- 共生型サービスの利用等の観点から、障害者総合支援法の指定特定相談支援事業者も連携の対象に含まれる。
問21
居宅サービス計画の作成について適切なものはどれか。3つ選べ。
1課題分析の結果は、居宅サービス計画書に記載しない。
2総合的な援助の方針は、利用者及び家族を含むケアチームが確認、検討の上、居宅サービス計画書に記載する。
3居宅サービス計画の長期目標は、基本的に個々の解決すべき課題に対応して設定するものである。
4週間サービス計画表には、提供されるサービス以外に主な日常生活上の活動も記載する。
5サービス担当者会議の要点には、出席できないサービス担当者に対して行った照会の内容について記載しなくてよい。
問22
指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について正しいものはどれか。2つ選べ。
1モニタリングは、少なくとも月に1回行わなければならない。
2アセスメントは、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。
3計画の交付は、家族に行えばよい。
4地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。
5介護支援専門員以外の者も作成できる。
問23
Aさん(72歳、男性、 要介護2、 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa)は、妻(63歳)と二人暮らしで、小規模多機能型居宅介護事業所に登録し、週2回の通いサービスと週3回の訪問サービスを利用している。Aさんは、若い頃より散歩が趣味であったが、最近、散歩に出かけると自宅に戻れなくなることが増え、警察に保護されることがあった。妻は日中就労(週5日)のため、見守ることができずに困っている。この時点における計画作成担当者である介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。3つ選べ。
1徘徊感知機器の情報を収集し、Aさんと妻に情報提供を行う。
2Aさんや妻の同意を得ないで、Aさんの立ち寄りそうな店舗などに、Aさんの写真と妻の携帯電話番号を掲示してもらう。
3Aさんの心身の状況や自宅周辺の環境をアセスメントし、自宅に戻れなかった理由を探る。
4通いサービスの利用日以外は外出をしないように、Aさんを説得する。
5近隣住民等による見守り体制が取れるかどうか民生委員に相談する。
問24
Aさん(80歳、女性)は最近、閉じこもりがちになり、体力が低下してきた。同居する娘は心配になって市役所に相談し、要支援lの認定を受けた。地域包括支援センターから委託を受けて、介護支援専門員が訪問したところ、娘は「母にはいつまでも元気でいてもらいたいが特に希望するサービスはない」と言う。介護支援専門員の対応として、より適切なものはどれか。2つ選べ。
1特に希望するサービスがないので、今のところ支援の必要がないと考え、しばらく様子を見るよう娘に伝える。
2指定訪問介護の生活援助を紹介する。
3指定認知症対応型共同生活介護を紹介する。
4Aさんの社会参加の状況や対人関係を把握する。
5地域ケア会議などにおいて生活機能の改善のために必要な支援を検討する。
問25
特別養護老人ホームに入所しているAさん(80歳、女性、要介護4)は、がんの末期で余命1か月程度と医師から告げられている。Aさんは自宅で最期を迎えたいと希望している。自宅で一人暮らしをしている夫は、Aさんの希望に沿いたいと考えているが、 自宅での介護や看取りに不安を抱いている。Aさんの居宅介護支援の依頼を受けた介護支援専門員がAさんや夫との面談を進めるに当たっての対応として、より適切なものはどれか。3つ選べ。
1夫が何を不安に感じているのかを聴き取る。
2施設の嘱託医に居宅療養管理指導を依頼する。
3夫の負担を考慮し、施設での看取りを依頼する。
4Aさんが自宅でどのように過ごしたいのかを聴き取る。
5Aさんの自宅がある地域で看取りに対応している診療所の情報を収集する。
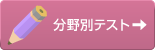
正解は…3・5